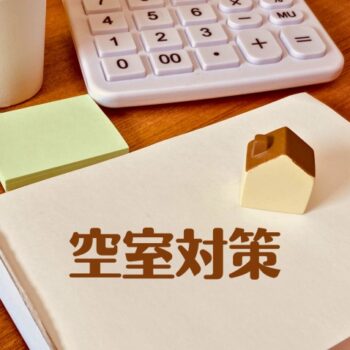家づくりは人生における一大プロジェクト。多くの方が「何から始めたらいいのかわからない」「どのくらいの期間がかかるの?」と不安や疑問を抱えながらスタートします。そんな不安を解消するために、本記事では、家づくりを成功させるために知っておきたい「家づくりの流れ」について、初心者にもわかりやすく解説します。
設計から資金計画、土地探し、引き渡し、そしてその後のアフターケアに至るまで、各ステップを丁寧に紐解くことで、全体像が把握できるようになります。これから家づくりを始めようとしている方、あるいはすでに検討中の方にとって、失敗しない家づくりのためのガイドラインとなるはずです。
家づくりの基本的な流れを押さえて安心スタート
情報収集・家族での話し合いで理想の住まい像を共有しよう
家づくりを始めるうえで、最初に重要なのは「どんな家にしたいか」を明確にすることです。そのためには、まず多くの情報に触れることからスタートします。住宅展示場を巡ったり、InstagramやPinterestなどのSNSで住まいのイメージを集めたりすることで、自分たちの理想に近い住宅の「形」が見えてきます。
この段階で大切なのは、家族全員が同じ方向を向いているかを確認することです。「キッチンはアイランド型がいい」「子ども部屋は何部屋必要か」など、家族の生活スタイルや将来のライフプランを見据えて意見を出し合いましょう。実際に、住み始めてから「思っていたのと違った」と後悔するケースの多くは、この話し合い不足が原因です。
加えて、理想の暮らしを紙に書き出したり、写真を切り抜いてノートにまとめたりする「マイホームノート」を作成するのもおすすめです。これにより自分たちの想いを視覚的に確認でき、工務店や設計士への共有もしやすくなります。
理想の家づくりは、具体的なイメージと家族の合意から生まれます。最初のステップをしっかりと踏むことで、その後の流れもスムーズに進められるでしょう。
予算・資金計画の決定が家づくりの成功を左右する
家を建てるにあたり、最も現実的でかつ避けては通れないのが「お金」の問題です。ここでの資金計画は、単なる予算決めではなく、将来の生活まで見据えた重要な意思決定です。
まず最初に行うべきは、自己資金の確認と住宅ローンを含めた総予算の設定です。年収や家計の支出バランスを見ながら、「無理なく返済できる金額」をベースに計画を立てます。例えば、年収の25〜30%以内にローンの年間返済額を抑えるのが一般的とされています。また、教育資金や老後資金といった将来的な出費を無視した無理なローン設計は、生活の質を大きく損なうリスクがあります。
次に、土地代・建物代に加えて発生する諸費用を忘れてはいけません。登記費用や火災保険、引っ越し費用、外構工事費用など、見落としがちな項目も含めると、総費用の1〜2割程度が追加で必要になります。
資金計画は、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、より精度の高いものにすることができます。プロの視点で生活設計まで含めてアドバイスをもらうことで、将来にわたって安心できる家づくりが実現します。
予算と聞くとつい制限のように感じてしまいがちですが、計画的に行えば「安心して家を建てるための指標」となります。計画に時間をかけることは、家づくり成功への大きな一歩です。
工務店の選定・決定で信頼できるパートナーを見つける
理想の家を現実の形にしてくれるパートナー、それが工務店やハウスメーカーです。無数に存在する建築会社の中から、どこに依頼すればいいのか迷う方も多いでしょう。ここでは「比較・検討・信頼」がカギになります。
まず注目すべきは、その会社の「施工実績」です。過去にどんな家を建てているか、得意なスタイルは何かなど、ホームページやSNS、カタログを活用して事前情報を集めましょう。次に、実際に施工した家を見学できる「完成見学会」や「オープンハウス」に足を運ぶことで、質感や仕上がり、提案力を体感できます。
さらに大切なのが「担当者との相性」です。こちらの要望をしっかりと汲み取り、誠実に対応してくれるかは非常に重要です。最初の打ち合わせで感じた印象や、提案内容のわかりやすさ、質問への対応スピードなどを基準に比較しましょう。
複数社に見積りやプランを依頼する「相見積り」は、価格だけでなく設計提案力を比較するうえでも有効です。その際、価格の安さだけで選ぶのではなく、「価格と内容のバランス」が取れているかを見ることが大切です。
信頼できる工務店との出会いは、家づくりの満足度を大きく左右します。焦らずじっくりと時間をかけ、自分たちにぴったりのパートナーを見つけましょう。
住宅ローンの事前審査で資金面の不安を払拭しよう
家づくりをスムーズに進めるには、「住宅ローンの事前審査」を早い段階で済ませておくことが重要です。これは、金融機関が借入可能かどうかを簡易的に判断する審査で、実際に融資が下りるかの目安になります。
事前審査では、年収や勤続年数、過去の借入状況などをもとに、借入可能額や金利の条件が提示されます。希望の土地や建物が見つかったとき、すぐに申し込みに移れるよう、早めにこの準備をしておくことが求められます。
審査に通過することで、「この金額までなら家を建てられる」という資金の上限が明確になり、土地選びや間取りの検討にも具体性が生まれます。また、購入意思を示す「買付申込書」を提出する際にも、ローン事前審査の通過証明があると信頼性が高まり、交渉も有利に進められます。
一方で、審査に落ちるケースもあるため、複数の金融機関に相談する、あるいは借入額を調整するなどの対応も視野に入れておくと良いでしょう。事前審査を通じて、自分たちの資金状況を客観的に把握することは、安心して家づくりを進めるための第一歩です。
土地探しから購入まで家づくりの流れで重要な段階
土地探しは住みたいエリアの優先順位を決めてから
土地探しは家づくりにおいて最初の大きなハードルです。どんなに理想的な家を設計しても、建てる土地が合わなければ計画そのものが成り立ちません。最も大切なのは「どこに住みたいか」というエリア選定です。これを明確にしないまま探し始めると、何を基準に判断してよいか分からなくなり、情報に振り回されてしまいます。
まずは、通勤・通学の利便性、買い物や病院の距離、子育て環境、自然環境のバランスなど、生活スタイルに直結する条件を家族で話し合いましょう。「駅から徒歩10分以内」「近くに保育園がある」「静かな住宅街」など、具体的な優先条件を整理することで、エリアを絞りやすくなります。
次に、複数の不動産サイトを使って相場感を養いましょう。同じ条件でも市区町村によって価格差は大きく、エリアを広げることで思わぬ掘り出し物に出会えることもあります。さらに、建築予定の工務店が土地探しもサポートしてくれるケースも多く、地域に精通した担当者のネットワークは非常に頼りになります。
土地は「一点物」です。焦って選ぶと後悔に繋がる可能性が高いため、慎重に比較・検討を重ねることが、納得のいく土地探しへとつながります。
土地の買付申込みはスピード勝負になることも
理想の土地が見つかったとき、次に行うのが「買付申込み」です。これは購入の意思を明確に示す手続きで、契約を確定するものではありませんが、交渉の優先権を確保するために重要なステップです。
良い土地は他の購入希望者とも競合しやすいため、タイミングが極めて重要になります。買付申込書を提出することで、「この人が購入希望者である」と不動産会社や売主にアピールでき、条件交渉にも入りやすくなります。提出の際には希望購入価格や条件(引き渡し時期など)を記載するのが一般的です。
とはいえ、衝動的に買付申込みをしてはいけません。その土地に法的制限や建築不可の条件がないか、上下水道や電気・ガスのインフラが整っているか、災害リスクはどうかなど、しっかり確認する必要があります。場合によっては工務店と一緒に現地を見に行き、建てたい家が建てられるかのアドバイスをもらうと安心です。
決断のスピードと、事前のチェックを両立させるためには、普段から土地に関する基礎知識を身につけておくことが肝心です。
土地の購入契約で気をつけるべきポイントとは
買付申込み後、条件がまとまればいよいよ「土地の売買契約」に進みます。この契約が正式に成立すると、キャンセルには違約金が発生する場合もあるため、契約内容の確認は慎重に行わなければなりません。
まず確認すべきは「手付金」についてです。通常、土地代金の5%〜10%程度を契約時に支払いますが、この金額は後に総額から差し引かれます。また、契約解除に関する取り決め(解約手付や違約金)も明記されており、双方が理解した上で契約を交わす必要があります。
次にチェックすべきなのが、土地の境界や権利関係です。筆界未確定の土地や、隣接地との境界が曖昧な場合は、トラブルになることもあります。できれば「境界確定測量図」の有無を確認し、隣地とのトラブルを防ぎましょう。
そのほかにも、建築条件付き土地であれば、特定の建築会社と一定期間内に契約しなければならない条件が課されていることがあります。この場合、自由設計の自由度が制限されるため注意が必要です。
契約前には、不動産会社の宅地建物取引士が説明する「重要事項説明書」にも細かく目を通し、不明点があれば遠慮なく質問しましょう。納得のうえで署名・捺印を行うことが、後悔のない土地購入につながります。
敷地調査で安全性と建築条件をしっかりチェック
土地購入が決まったら、すぐに着手すべきなのが「敷地調査(法的・物理的調査)」です。これは、購入した土地に安全に、そして法律に則って家が建てられるかどうかを調べる重要なプロセスです。
調査項目としては、第一に「建築基準法や都市計画法による規制」があります。用途地域や建ぺい率・容積率、道路との接道義務など、法的制限により設計できる建物の大きさや形が変わるため、事前確認は不可欠です。
次に行うのが「地盤調査」です。地盤の強度が不足している場合、家が傾いたり沈んだりするリスクがあるため、必要に応じて地盤改良工事が必要になります。これは数十万円単位の追加費用になることもあるため、早めの見積もりが望ましいです。
また、土地の形状や高低差、周辺建物の位置などもチェックポイントです。特に日当たりや風通し、プライバシーの確保といった観点から、実際に建てる家の配置に大きく影響を与えます。
調査の結果をもとに、建築士や工務店と相談しながら「その土地に最適な家のプラン」を検討することで、より安全かつ快適な住まいづくりが可能になります。
有限会社ひかり不動産は、埼玉県美里町を中心に本庄市や児玉郡内の「不動産売買」「不動産買取」自然素材の「注文住宅」「リフォーム」などを手がける会社です。
お気軽にお問い合わせください。

家づくりの流れにおける設計と契約のステップを理解しよう
間取りの打ち合わせ・予算決定で暮らしを形にする
家づくりの中核とも言えるのが、「間取りの設計」です。ここでは、自分たちの理想のライフスタイルを具体的な形に落とし込む作業が進められます。暮らしやすさ、動線、収納、日当たり、風通し、将来の家族構成の変化など、多角的な視点で検討を重ねることが重要です。
まずは要望をしっかり言語化しましょう。例えば「子ども部屋は2つ必要」「玄関からすぐに手洗いできる導線を設けたい」「趣味の部屋が欲しい」といった具体的な暮らしの希望をリスト化します。そして、それに優先順位をつけていくことで、限られた敷地と予算の中で取捨選択がしやすくなります。
設計士やコーディネーターとの打ち合わせでは、要望がどれだけ現実的か、どこにコストがかかるかを明確にしながら進めていきます。坪数を抑えつつも空間を有効活用するアイデアや、建築素材の選定によりコストコントロールも可能になります。
この段階で、建物の概算費用と合わせて、地盤改良費、外構費用、インテリア費用なども含めた総額予算を確認することが大切です。ここで予算オーバーとなれば、再調整が必要になり、工事全体のスケジュールにも影響が出てしまいます。
「理想」と「現実」を調整しながら、自分たちにとってベストな住まいを形にしていく過程が、間取り決定のステップです。
住宅ローンの本申込み・工事請負契約の締結でいよいよ本格始動
間取りと仕様が固まり、概算費用が見えてきた段階で、次に行うのが「住宅ローンの本申込み」と「工事請負契約」の締結です。ここから家づくりは“構想”から“実行”のフェーズへと進んでいきます。
住宅ローンの本申込みは、事前審査を通過している場合でも、あらためて詳細な審査が行われます。物件の価格や担保価値、借入希望額、申込者の収入・勤務先などが再チェックされ、正式な融資承認が下りることになります。審査の結果によっては、希望通りの金額が借りられないケースもあるため、再見積もりやプラン変更も視野に入れておくと安心です。
ローンの審査と並行して、工務店やハウスメーカーと「工事請負契約」を締結します。この契約は、どのような内容の建物をいくらで、どのような工程で建てるのかを定めたもので、建築工事における最も重要な法的書類です。契約書には、工事の内容、金額、工期、引き渡し日、保証、解約条件などが細かく記載されています。
この契約を結んだ時点で、多くの工務店では設計図が完成し、建築確認申請に向けた準備がスタートします。契約書の内容は、住宅完成後のトラブルを避けるためにも、疑問点を残さずすべて理解・納得してから署名を行うことが大切です。
本申込みと請負契約が完了すると、いよいよ現場が動き出します。これ以降の変更はコストや工期に影響するため、この段階までに「本当に住みたい家の姿」を固めておくことが求められます。
確認申請提出・建物詳細設計打ち合わせで法的準備も万全に
工事請負契約を締結した後、建築予定の住宅が法令に適合しているかを確認する「建築確認申請」の手続きが必要です。これは、建物の安全性を担保するために法律で義務づけられているもので、地方自治体または指定確認検査機関に対して行います。
申請書には、建物の設計図、構造計算書、敷地図、配置図などが添付され、構造や安全性、耐火性、建ぺい率・容積率などの観点からチェックが行われます。申請から確認が下りるまでには、一般的に2〜3週間ほどかかります。この「確認済証」を得なければ、建物の着工はできません。
同時に進めるのが「建物の詳細設計打ち合わせ」です。ここでは、外壁材、屋根材、窓サッシ、玄関ドア、キッチンやトイレ、浴室など、家を構成する各パーツを1つ1つ決めていきます。また、照明計画やコンセントの位置、インターホンや宅配ボックスの設置場所など、暮らしに関わる細部の仕様を詰めていきます。
この段階で後悔しがちなのが、「もっとこうしておけばよかった」という細かな設計ミスです。図面上では気づきにくい生活動線や家具配置、採光のバランスなどを実際の生活をイメージしながら確認しましょう。
確認申請の確認が下り、詳細設計が完了すれば、いよいよ着工の準備が整います。ここまでのステップは、一つひとつが将来の暮らしを支える「土台」です。丁寧に、かつ納得のいく選択を重ねていくことが、満足度の高い住まいへと繋がっていきます。
着工から引き渡しまでの家づくりの流れをチェック
着工〜工事中は進捗チェックと現場確認がカギ
住宅の着工が始まると、いよいよ形として「家づくり」が見えるフェーズに突入します。しかし、この工程で油断してはいけません。なぜなら、図面通りに建物が仕上がっているか、工期通りに進んでいるかを確認する責任は施主にもあるからです。
工事はまず「地鎮祭」でスタートします。これは土地の神様に建築の安全を祈願する儀式で、施工会社が手配してくれることが一般的です。その後、基礎工事、上棟、内外装工事へと進み、各工程で専門の職人が入れ替わり作業を行います。
この期間に最も重要なのが「現場確認」です。定期的に現場に足を運び、工務店や現場監督と進捗を確認することで、図面とのズレや仕様変更のタイミングを早めに把握できます。また、配線の位置や壁紙の色など、細かい部分で「聞いていた話と違う」といったトラブルを未然に防ぐ効果もあります。
さらに、工程ごとに写真を撮影しておくと、万一不具合が出た際に原因特定の材料になりますし、将来のリフォーム時にも役立ちます。現場で気になる点があればすぐに質問・確認する姿勢が、施工精度の向上にもつながります。
「現場に行くのは気が引ける」という方もいますが、信頼関係が築けていればむしろ大歓迎されることがほとんどです。後悔のない住まいをつくるためには、積極的な現場参加が不可欠です。
引き渡しでついに夢のマイホームが完成!
すべての工事が完了し、検査を経て迎えるのが「引き渡し」の日です。これは新居の鍵を正式に受け取り、施主が法的にも建物の所有者となる瞬間であり、家づくりの集大成とも言える大切な工程です。
引き渡し前には、「完了検査」が実施されます。これは建物が建築基準法に適合しているかを行政または指定確認検査機関が確認するもので、検査に合格しないと住民票の移動や引っ越しもできません。合格すれば「検査済証」が発行され、建物の法的な完成が認められます。
その後、施工会社と共に「施主検査」を行います。ここでは、壁や床、設備などに傷や汚れがないか、扉や窓の開閉がスムーズか、水漏れはないかなど、細かく確認していきます。見落としがちなポイントは、コンセントの数や位置、照明スイッチの配置、クロスの浮きやズレです。引っ越してから後悔しないよう、気になる点は遠慮なく伝え、必要に応じて補修依頼を出しましょう。
引き渡し当日には、家の鍵とともに、保証書や設備の取扱説明書、メンテナンスマニュアルが手渡されます。また、引っ越し後の点検スケジュールや緊急時の連絡先についても案内されるため、しっかり確認しておきましょう。
完成した住まいを前にする感動は、言葉では言い表せないほど大きなものです。そして、その喜びを確かなものにするためには、ここまでの丁寧な準備と確認作業が欠かせません。家づくりのラストシーンを最高の形で迎えるために、最後まで妥協せず、確認を怠らないようにしましょう。
入居後も続く家づくりの流れ定期点検とメンテナンスが重要
定期点検・アフターメンテナンスで長く快適に住まう
家を建て終えたら、すべてが完了と思われがちですが、実は「家づくり」は入居後からが本当のスタートとも言えます。というのも、どんなに優れた設計・施工で建てられた住宅であっても、年月の経過とともに劣化や不具合が出てくることは避けられないからです。そのため、定期的な点検と適切なメンテナンスが、家を長持ちさせ、快適に住み続けるための鍵となります。
多くの住宅会社では、入居後1年、2年、5年、10年といった節目ごとに「無料定期点検」を提供しています。内容は、外壁のひび割れ、雨漏り、建具の動作、給排水の不具合、屋根の状態など、目視や動作確認を通じて問題の有無をチェックします。点検を受けることで、将来的な大きな修繕を未然に防ぐことができ、結果としてコストを抑えることにもつながります。
また、アフターメンテナンスは「保証制度」と密接に関係しています。たとえば、住宅瑕疵担保責任保険では、構造躯体と雨漏りに対して10年間の保証が義務づけられています。しかし、その保証を受けるためには、点検の記録や、定期的なメンテナンスの実施が条件となる場合が多いです。
加えて、自主的にメンテナンスを行うことも重要です。フィルターの清掃やコーキングの劣化チェック、排水管の洗浄など、日常的にできる範囲のメンテナンスを習慣づけることで、家の健康状態を保つことができます。
家は、ただ「建てるもの」ではなく、「育てていくもの」です。愛着を持って手入れを続けることで、家族の思い出が積み重なり、住まいに一層の価値が生まれていきます。長く快適に暮らすためにも、入居後の点検とメンテナンスを怠らず、住まいを大切にしていきましょう。
家づくりの流れは入居希望時期から逆算して計画する
家づくりを成功させるためには、最初に「いつ住みたいのか」というゴールを設定することが極めて重要です。入居時期を明確にすることで、その目標から逆算して計画を立てることができ、無駄な時間や予期せぬトラブルを回避する手助けになります。
たとえば「子どもが小学校に入学するタイミングで新居に引っ越したい」「年度内に引き渡しを受けたい」「冬の寒さが本格化する前に入居したい」など、ライフイベントや季節によって入居希望時期はさまざまです。ここで大切なのは、その希望をただ掲げるのではなく、そこからスケジュールを逆算して現実的な計画を組み立てることです。
一般的に家づくりには、情報収集から入居までおよそ10ヶ月〜1年程度を要します。土地探しに3ヶ月、設計・打ち合わせに2〜3ヶ月、確認申請と着工準備に1ヶ月、建築工事に4〜5ヶ月といった具合に、各段階ごとに時間がかかります。さらに、住宅ローン審査や地盤改良など、想定外の工程が加わることもあるため、余裕を持ったスケジュール設計が求められます。
逆算式で計画を立てると、今なにをすべきかが明確になり、焦りや迷いを最小限に抑えることができます。特に年度替わりの3月や、引っ越しが多い夏休み前後は工事業者や引越業者の予約が取りにくくなるため、早めの着手が大きな差を生みます。
計画の初期段階では、建築会社やファイナンシャルプランナーと一緒にタイムラインを作成するのもおすすめです。プロの視点から無理のないスケジュール調整ができ、必要な手続きの時期も見逃しません。
理想のマイホームを理想のタイミングで手に入れるためには、感覚ではなく「計画的な時間管理」が何よりも大切です。入居希望日をゴールに据えることで、家づくり全体の流れが整理され、ブレない家づくりを実現できます。
家づくりの流れを知って理想の住まいを計画しよう
家を建てるという経験は、多くの人にとって一生に一度あるかないかの大きな出来事です。その大きな決断を「なんとなく」で進めてしまうと、理想とはほど遠い住まいになってしまう可能性があります。だからこそ、家づくりの「流れ」を理解したうえで計画を立てることが、満足度の高い家づくりへの第一歩となります。
まず知っておきたいのは、家づくりには多くのステップが存在し、それぞれに時間・お金・エネルギーが必要だということです。情報収集、資金計画、土地探し、設計、契約、施工、引き渡しといった工程は、それぞれが独立しているのではなく密接に関連しています。一つの段階で判断を誤ると、次の段階にも影響が及び、結果としてトータルの満足度が下がってしまうリスクがあります。
そこで重要なのが、「全体像の把握」です。まず全体のフローを頭に入れ、それぞれの段階で何をすべきか、どんな準備が必要かを整理します。すると、事前にすべきことが明確になり、余裕を持って各ステップに臨めるようになります。
例えば、土地が決まる前に間取りを考え始めてしまうと、希望通りの設計ができないこともあります。また、資金計画が曖昧なままだと、理想の家を目指しても途中で予算オーバーにより設計変更を余儀なくされることがあります。こうしたミスマッチを防ぐためにも、家づくりの一連の流れを先に理解することが必要なのです。
さらに、全体像を理解しておくことは、「段取りの良さ」にもつながります。スムーズな打ち合わせ、的確な判断、効率的な時間の使い方ができるようになることで、工期の遅延や不必要なストレスも回避できます。最終的には、コストパフォーマンスの良い家づくりにもつながり、暮らし始めた後の満足度を大きく高めることができるのです。
理想の住まいは、「思いつき」ではなく「計画」から生まれます。しっかりと流れを理解し、必要な知識と準備を持って挑むことが、後悔しない家づくりの最大のポイントです。
家づくりの流れまとめ家づくり成功の秘訣をおさらい
家づくりは、単に建物を完成させることが目的ではありません。その先にある「豊かで快適な暮らし」を実現するためのプロセス全体を指します。だからこそ、家づくりにおいて最も大切なのは、「流れ」をしっかりと理解し、各ステップを確実に踏んでいくことです。
これまで解説してきた通り、家づくりには情報収集、資金計画、土地探し、設計、契約、施工、引き渡し、アフターケアと、実に多くの段階が存在します。それぞれの段階には特有の課題や選択があり、そのひとつひとつが後の工程に影響を及ぼします。つまり、家づくりは点ではなく線、さらには流れとしてとらえるべきものなのです。
その上で忘れてはならないのが、「目的意識」と「準備力」です。家族にとってどんな家が必要か、どのタイミングで何をすればよいのかを明確にし、それに応じて事前に準備を整えることで、無駄なく、後悔のない家づくりが可能になります。また、準備を怠らなければ、施工中の変更や追加費用といったリスクも大幅に抑えることができ、精神的なゆとりにもつながります。
さらに、家づくりは「信頼できるパートナー選び」も鍵を握ります。建築会社や工務店、設計士、不動産会社、金融機関、全ての関係者としっかりとコミュニケーションを取り、同じゴールを共有できているかを常に意識することが重要です。
最終的に、「住んでからが本番」です。点検やメンテナンス、生活スタイルの変化への対応など、住み始めた後のことまでを含めて家づくりは続きます。だからこそ、入居後の未来を見据えた設計や資金計画が、真の意味での成功につながるのです。
理想のマイホームは、一夜にしてできるものではありません。着実に流れをたどりながら、一歩一歩積み重ねていくことが、満足のいく家づくりの最大の秘訣なのです。


投稿者プロフィール

-
有限会社ひかり不動産 代表取締役
宅地建物取引士 二級建築士
埼玉県美里町に生まれ育ち
1987年~1990年:住宅建築・不動産会社勤務
1990年~:有限会社ひかり不動産
2000年~現在:有限会社ひかり不動産 代表取締役
不動産・住宅建築業界一筋で業界歴35年超のベテラン
長年の経験と今まで培ってきた事 そして、こだわりのある
「自然素材の家づくり」について皆様にお伝えします
最新の投稿
 不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう
不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう 家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド
家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド 不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説
不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説 家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド
家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド