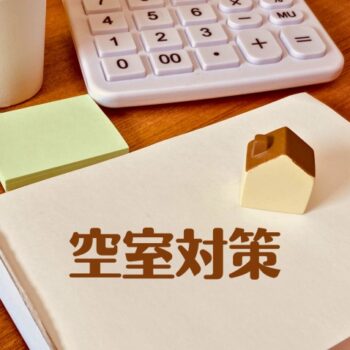空き家を相続したものの、どのように処分すべきか、税金面での不安を抱えている方は少なくありません。特に都市部では、相続した空き家が高値で売れる一方で、高額な譲渡所得税が課される可能性があるため、売却をためらうケースもあります。そこで注目されているのが、「空き家の譲渡所得に対する3,000万円特別控除」という制度です。この控除を上手に活用すれば、大幅に税金を抑えて空き家を売却することが可能になります。
本記事では、この制度の内容や適用条件、実際の手続き、必要書類、注意点などを包括的に解説します。制度の仕組みを正しく理解して、後悔のない空き家売却を実現しましょう。
空き家売却で3000万円控除が適用される対象税目について解説
空き家を相続した際、その不動産を売却することで得られる利益に対して課税されるのが「譲渡所得税」です。この譲渡所得税は、所有期間や取得費、譲渡費用に応じて計算され、売却益が多ければ多いほど課税額も増加します。特に都市部における不動産価格の高騰を受け、空き家であっても数百万~数千万円の利益が出るケースも珍しくありません。
こうした背景の中で、国が用意したのが「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」の制度です。これは一定の条件を満たす相続空き家について、売却時に最大3,000万円まで譲渡所得から控除できるというものです。たとえば、譲渡益が3,000万円以下であれば、理論上、譲渡所得税を一切支払う必要がないということになります。
この特例が適用されるのは、個人が取得した相続財産である空き家に限られており、法人が保有する不動産や投資用物件の売却には適用されません。対象となるのは「譲渡所得税」および、それに付随する「住民税」「復興特別所得税」です。つまり、この控除が活用できれば、所得税・住民税あわせて数百万円単位の節税効果が期待できるわけです。
制度導入の背景には、高齢化社会と人口減少により全国的に増加している「管理不全な空き家」の問題があります。これらの空き家は、倒壊のリスクや防災上の危険、景観の悪化など多くの課題を抱えており、行政としてもその流通促進を図る必要がありました。特例制度は、これらの空き家を市場に流通させ、相続人による売却を後押しするための重要な施策です。
一方で、制度を適用するには、単に空き家を売却するだけではなく、細かな条件や手続きをクリアしなければなりません。売却時期、対象物件の構造・築年数、相続から売却までの状況など、一定の条件が揃って初めて控除が認められます。制度の内容を正しく理解しないまま進めると、後になって「控除が使えなかった」という事態にもなりかねません。
したがって、相続した空き家を売却する場合は、まず自分がこの特例制度の対象に該当するのか、そしてどのような税目にどれほどの影響があるのかをしっかりと確認することが大切です。税理士など専門家の力を借りながら、譲渡所得税の計算と控除の適用可能性を見極め、適切な手続きを行うことが、最大限の節税とリスク回避に繋がります。
空き家売却で3000万円控除の概要と基礎知識
特例の対象となる被相続人居住用家屋および敷地等について
空き家の売却に伴って適用される3,000万円の特別控除は、すべての空き家に対して適用されるわけではありません。この特例の適用を受けるには、「被相続人居住用家屋」およびその敷地という明確な要件を満たす必要があります。具体的には、亡くなった方が生前に一人で住んでいた家屋であり、かつ相続後に居住や貸出などをしていない「完全な空き家」であることが基本条件です。
また、建物の築年数も重要なポイントです。昭和56年5月31日以前に建築された住宅に限られます。これは、旧耐震基準で建てられた建物が災害時に倒壊リスクが高いため、取り壊しや売却を促進することが目的です。該当する家屋を取り壊して更地で売却した場合でも、相続時にその家屋が対象の条件を満たしていたと認められれば、敷地部分に対しても控除の対象となります。
このように、家屋そのものの状態や築年、相続後の使用状況までを総合的に確認した上で、控除の適用可否が判断されます。そのため、相続後すぐに売却計画を立てるのではなく、対象となるかどうかの確認と必要書類の整備が必要不可欠です。
空き家売却で3000万円控除を受けるための適用要件とは
この特例制度には、適用を受けるための要件が細かく定められています。第一に、被相続人が亡くなる直前にその家屋に一人で住んでいたこと。夫婦や家族との同居であった場合、特例の対象から外れる可能性があります。次に、家屋が旧耐震基準に該当する、つまり1981年(昭和56年)5月31日以前に建築されたものであることが求められます。
さらに、相続人が相続後その家屋に住んだり貸したりせず、譲渡まで「空き家のまま」維持されている必要があります。譲渡時点での家屋の用途が、控除適用の可否を左右するからです。そして、売却価格が1億円以下であること、親族や同族会社への譲渡ではないことも条件に含まれています。これにより、制度の乱用や節税目的の不正適用を防いでいます。
最後に、譲渡の期限にも注意が必要です。相続の開始から3年が経過する日の属する年の12月31日までに売却が完了している必要があります。つまり、相続後3年以内に売却計画を立て、手続きを済ませることが実務上のハードルとなるのです。
これらの要件を一つでも満たしていなければ、制度の適用は認められません。よって、売却を検討する際には、不動産業者や税理士と相談しながら、早い段階で要件に照らし合わせた確認を行うことが重要です。控除額が大きいため、事前準備の有無が数百万円単位の税負担に直結することもあるため、慎重な対応が求められます。
有限会社ひかり不動産は、埼玉県美里町を中心に本庄市や児玉郡内の不動産の取り扱いと住宅建築を手掛ける創業50余年の地域密着企業です。土地や空家の買取りもお任せください。
住宅建築では、自然素材をふんだんに使用した注文住宅やリフォームを手掛けています。

空き家売却で3000万円控除の対象となる人と対象物について
空き家売却による3,000万円控除は、すべての空き家やすべての相続人に自動的に適用されるものではありません。対象となるのは、一定の条件を満たした「人」と「物件」の組み合わせであり、この制度を正しく利用するためには、その前提をしっかり理解する必要があります。
まず、対象となる「人」についてです。この特例が適用されるのは、空き家を相続した個人に限られます。法人が相続した場合や、相続を受けてすぐに法人へ売却したようなケースでは対象外となります。また、相続人が複数いる場合には、共有者全員が要件を満たしている必要があります。たとえば、兄弟姉妹で共有している空き家を売却する際、1人が居住したり貸したりしていた場合、その行為が全体の要件違反と判断される可能性があるため注意が必要です。
さらに、適用対象となる「物件」にも明確な条件があります。対象物件は、相続人が取得した「被相続人居住用家屋」およびその敷地に限られます。家屋は原則として昭和56年5月31日以前に建築され、かつ旧耐震基準に該当することが条件です。つまり、現行耐震基準で建てられた新しめの物件や、別荘・賃貸住宅などの用途で使われていた物件は原則として対象外となります。
また、建物を解体した上で土地だけを売却するケースも少なくありませんが、その場合も相続当初に該当する家屋が存在し、相続人が取り壊した経緯が明らかであれば、敷地に対して特例が適用されます。ただし、家屋が解体後すぐに駐車場や他用途に使用されていた場合、空き家のままではなかったと判断され、控除が否認されるリスクがあるため注意が必要です。
このように、「誰が」「どのような物件を」売却するのかという観点から、空き家売却で3,000万円控除が適用されるかどうかは決まります。相続が発生したら、対象者が制度の適用を受けられるか、物件の築年や用途が条件を満たしているかを早い段階でチェックすることが、後のトラブルを防ぐ鍵となります。
万が一、不明点や判断に迷う点がある場合は、税理士や不動産専門の行政書士に相談することで、スムーズかつ適切に進めることができます。特例の適用可否が税負担に大きな差を生むため、曖昧なまま進めることのないよう、専門家の意見を仰ぎながら慎重に判断していくことが求められます。
空き家売却で3000万円控除を受けるための手続きの流れ
確定申告や申請に関する方法とは
空き家売却による3,000万円控除を実際に受けるためには、売却後に適切な手続きを行い、確定申告にて申請を行う必要があります。制度そのものは非常に有利ですが、適用には正確な処理と書類の提出が求められるため、事前に手順を理解しておくことが重要です。
まず、売却が完了した後、譲渡所得に関する確定申告を行うのがスタートです。対象となるのは、その年の確定申告期間(通常は翌年の2月16日から3月15日まで)で、申告は売却益が出た年に行います。ここでポイントとなるのは、控除を適用するためには「特例適用の意思表示」と「必要書類の添付」が必須であるということです。控除を申告し忘れたり、書類が不足していた場合、控除は認められません。
必要となる申告書は「確定申告書B」と「分離課税用の譲渡所得の内訳書」です。ここに3,000万円控除の対象である旨を記載し、売却に関する詳細(売却価格、取得費、譲渡費用など)を正確に入力します。特例の適用を受けるかどうかで、納税額に大きな差が出るため、記載内容のミスがないよう注意が必要です。
また、e-Tax(電子申告)を利用する場合も、書類のPDF添付や電子署名などが求められます。紙申告よりもスムーズに手続きできる反面、デジタルリテラシーが必要になるため、慣れていない方は事前に国税庁のマニュアルや動画で操作方法を確認しておくことが望ましいです。
空き家売却で3000万円控除を受けるための申告先等について
申告書の提出先は、原則として被相続人の死亡時の住所地を所轄する税務署です。つまり、売却者(相続人)の現住所ではなく、被相続人が住んでいた場所に応じて申告先が決まる点が特徴です。例えば、相続人が東京に住んでいても、被相続人が大阪在住だった場合、大阪の税務署に申告する必要があります。
申告の際には、譲渡所得の計算根拠となる契約書、登記簿謄本、固定資産評価証明書などの他、「被相続人居住用家屋等確認書」という自治体が発行する書類も添付する必要があります。この確認書の取得には、別途市区町村に申請が必要で、発行までに時間がかかることもありますので、早めの準備が求められます。
また、申告の際に不備があった場合、税務署から修正の連絡が来ることもありますが、それには時間がかかり、最悪の場合控除が無効になるケースもあります。特に、期限を過ぎた修正申告や不完全な申告書は、税務署の裁量で不受理となることもあるため、初回の提出時点での完全性が極めて重要です。
そのため、少しでも不安がある方は、税理士のサポートを受けながら申告書を作成することをおすすめします。税額の算出だけでなく、必要書類の整備、申告期限の管理などを任せられるため、確実かつ安心して特例を活用できる体制が整います。
空き家売却で3000万円控除を受ける際に必要な提出書類とは
空き家売却で3,000万円控除を受けるには、確定申告書の提出だけでなく、制度の適用要件を満たしていることを証明する各種書類を税務署に提出する必要があります。これは、制度の悪用や誤適用を防ぐためのもので、非常に厳格に運用されています。必要書類を一つでも欠くと控除が受けられない可能性があるため、慎重な準備が求められます。
まず必須となるのが、「被相続人居住用家屋等確認書」です。これは、対象となる家屋が制度の要件を満たしていることを市区町村が確認し、発行する公式文書です。取得には申請書の提出と共に、家屋の登記簿謄本や被相続人の住民票除票、建築年月がわかる書類(固定資産課税明細書など)を添付する必要があります。この確認書の取得には時間がかかることが多く、特に申告期限が迫ると発行までに1カ月以上かかることもあるため、早めの申請が不可欠です。
次に必要なのが、譲渡に関する書類です。具体的には売買契約書、譲渡代金の支払いが確認できる書類(領収書や振込明細書)、譲渡した物件の登記事項証明書などが求められます。これらは、売却が実際に行われたものであること、そして対象が確かに相続した空き家であることを裏付ける証拠となります。
また、被相続人に関する書類としては、住民票の除票および死亡の事実が確認できる戸籍謄本、さらには相続関係が明らかになる法定相続情報一覧図や遺産分割協議書なども提出することが望ましいとされています。これにより、空き家が正当に相続されたことと、申告者がその法的相続人であることを明確にできます。
加えて、確定申告書類には「譲渡所得の内訳書(分離課税用)」を添付し、3,000万円の特別控除の適用を明記する必要があります。この書類には、取得費や譲渡費用、譲渡価格などを詳細に記載し、譲渡所得がどのように算出されたかを明示しなければなりません。不明点があれば、早めに税理士に相談し、記載漏れや誤記を避けることが大切です。
書類の準備が整っていない場合、控除が否認され、後から修正申告や更正の請求をすることになりかねません。特に、書類不備による不受理は制度の利用そのものを失うリスクがあるため、「万全の準備」がこの制度を活用する上での鍵となります。制度の恩恵は大きい分、書類の不備による失敗も大きな損失に繋がることを忘れてはなりません。
空き家売却で3000万円控除の根拠となる法令等について解説
空き家の売却に伴う3,000万円控除という制度は、単なる行政の便宜措置ではなく、明確な法的根拠に基づいて定められています。この制度の基盤となっているのは、「租税特別措置法第35条の2の2」という条文です。これは、特定の条件を満たす被相続人居住用家屋の譲渡に際して、譲渡所得から最大3,000万円を控除できると明記しているものです。
この法律は、2016年度の税制改正で新設されたものであり、背景には全国的に増え続ける空き家問題の深刻化があります。空き家は防災上のリスクや治安、景観など多方面に悪影響を与えるとされており、その利活用を促すことが社会的な急務となっていました。国としては、個人が相続した古い住宅の流通や解体を促進することで、空き家の放置を防ぐとともに、税負担の軽減というインセンティブを与える施策を打ち出したのです。
法令の中では、控除を受けられる条件として、「昭和56年5月31日以前に建築されたこと」「相続後に居住や賃貸などの使用実績がないこと」「相続人が個人であること」などが明文化されており、要件を一つでも満たさない場合は制度の適用を受けることができません。また、売却時の譲渡対価が1億円以下であること、譲渡先が親族や同族会社でないことなども、明確に定められています。
このように、制度はしっかりとした法令に基づいて設けられており、適用を受けるためには「法律に従って正確に手続きすること」が不可欠です。適用された控除額に対して税務署が後に調査を行うこともあり、その際に提出した書類や記載内容に不備があると、追徴課税や過少申告加算税が発生するリスクも存在します。
したがって、この3,000万円控除制度は、活用すれば非常に大きな節税効果をもたらすものの、それだけに法律やルールに即した厳格な運用が求められる制度でもあります。制度の正しい理解と法的根拠に基づく準備・申告を行うことこそが、安全かつ確実な活用に繋がると言えるでしょう。
空き家売却で3000万円控除が適用される相続取得後の特例とは
空き家に関する3,000万円特別控除は、相続後すぐに売却しなければならないという誤解が広まっていますが、実際には一定の猶予期間が設けられており、「相続から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に譲渡を完了していれば、控除の対象となる特例制度です。これにより、相続人は相続直後に慌てて売却せずとも、時間をかけて適正な売却先や価格を見極めることが可能となります。
この特例は、「相続から時間が経っても空き家のままであった」という状態を維持していれば、建物が取り壊されたとしても、敷地に対しても控除を認める柔軟な運用がされることが特徴です。つまり、家屋を解体して更地にした場合でも、条件を満たしていれば譲渡所得から3,000万円の控除を受けることができます。ただし、取り壊し後にその土地が駐車場として使用されていたり、第三者に貸し出されていた場合は「空き家のまま」とは認められず、控除が無効になる可能性があります。
また、老人ホーム等への入居によって一時的に不在となっていた被相続人の家屋についても、要件を満たしていればこの特例の対象となるケースがあります。例えば、被相続人が要介護状態となり老人ホームに転居したものの、その後亡くなり、元の自宅が空き家となった場合などが該当します。ここでは、老人ホームの入居がやむを得ない事情であったことや、自宅が第三者に使用されていないことを証明する書類(介護施設の入居証明書や施設契約書など)が求められます。
このように、本特例は非常に実務的かつ柔軟な制度であり、相続人の事情に配慮した設計になっているのが特徴です。ただし、「空き家のまま」という状態を維持しているかどうか、つまり使用実態の有無が制度の根幹をなしているため、一時的な使用や一見些細な用途変更でも控除が取り消される可能性があることに留意しなければなりません。
制度を適用するにあたり、自身のケースがどの条件に該当するかを正しく判断することが最も重要です。特に複雑な事情(たとえば、途中で一部相続人が居住した、土地の一部を駐車場として使用したなど)がある場合は、税務署や税理士に相談し、制度適用の可否を明確にしておくことで、後からのトラブルを防ぐことができます。
空き家売却で3000万円控除が適用される被相続人の住まいの条件とは
一人暮らしである必要性についての解説
空き家売却の3,000万円控除を受けるためには、被相続人が亡くなる前に「その家屋に一人で住んでいたこと」が必要です。この要件は、非常に重要かつ誤解されやすいポイントの一つです。例えば、被相続人が親族と同居していた場合や、家屋を他人に貸していた場合は、たとえ相続後に空き家状態であったとしても、この控除の対象外になります。
なぜこのような要件があるかというと、制度の目的が「誰も住まなくなった古い住宅の流通を促進すること」にあるからです。つまり、物理的に空き家であるだけではなく、被相続人が亡くなるまでその家に「一人で住んでいた」という証明が必要になります。これを確認するために、住民票の除票や介護記録などが使われます。
申告時には、被相続人の最終住所が該当物件であること、そしてその住所に他の住民が登録されていないことを証明しなければなりません。仮に住民票上では一人暮らしでも、実際に同居人がいたことが明らかになると、控除が否認されるリスクもあるため注意が必要です。
昭和56年以前に建築された家屋が条件となる理由
本制度では、昭和56年5月31日以前に建築された住宅に限り控除が適用されると定められています。これは1981年に施行された「新耐震基準」が大きく関係しています。この基準以前に建てられた家屋は、耐震性能が不十分であり、地震時に倒壊するリスクが高いとされているため、流通を促すことで災害時の被害軽減にも繋がるという政策的な背景があるのです。
古い建物ほど市場での売却が困難になる傾向があり、放置されがちですが、制度はそれを逆手に取り、節税メリットを与えることで解体または売却を促しています。売却後に買主が耐震補強や建替えを行うことで、地域の防災力が向上するという波及効果も狙いの一つです。
このため、建物の登記簿上の建築日や固定資産課税台帳をもって建築年を確認する作業が不可欠となります。該当しない年に建築された家屋については、たとえ空き家であっても控除の対象外となります。
相続後も空き家であり続けることの意味と背景
もう一つの重要な条件は、「相続から売却までの間、家屋が空き家であり続けること」です。たとえば、相続人が短期間でもその家屋に住んでしまった場合、それだけで控除の適用外とされてしまう可能性があります。制度としては、家屋の使用実績があると見なされた時点で「空き家ではない」と判断されるため、非常にシビアです。
このルールの背景には、「使用された住宅に対しては市場流通を促す必要がない」という制度趣旨があります。つまり、本当に活用されていない空き家のみを対象にすることで、制度の公平性と透明性を確保しているのです。
したがって、家屋を売却する予定があるなら、相続人が一時的に住んだり倉庫代わりに使ったりするのも避けるべきです。仮に一時的な使用でも税務署においては使用実績とみなされることがあります。
老人ホーム入居者も空き家売却で3000万円控除の対象となる場合とは
近年、注目されているのが「被相続人が老人ホーム等に入居していたケースでも控除が適用される」という特例です。これは、被相続人が要介護状態になり、やむを得ず老人ホームへ転居した場合でも、その自宅が一定期間空き家で維持されていれば控除対象とするという制度の柔軟な対応です。
ただし、この適用には「施設への入居が要介護等によるものであること」や「家屋が賃貸や居住に使用されていなかったこと」を証明する必要があります。具体的には、介護保険証の写しや施設の契約書、家屋の電気・水道使用履歴などが判断材料になります。
この特例により、実態として空き家であったにもかかわらず控除が受けられなかった高齢者家庭の救済が進み、実務上も多くの相続人にとって非常に有益な制度となっています。


投稿者プロフィール

-
有限会社ひかり不動産 代表取締役
宅地建物取引士 二級建築士
埼玉県美里町に生まれ育ち
1987年~1990年:住宅建築・不動産会社勤務
1990年~:有限会社ひかり不動産
2000年~現在:有限会社ひかり不動産 代表取締役
不動産・住宅建築業界一筋で業界歴35年超のベテラン
長年の経験と今まで培ってきた事 そして、こだわりのある
「自然素材の家づくり」について皆様にお伝えします
最新の投稿
 不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう
不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう 家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド
家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド 不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説
不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説 家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド
家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド