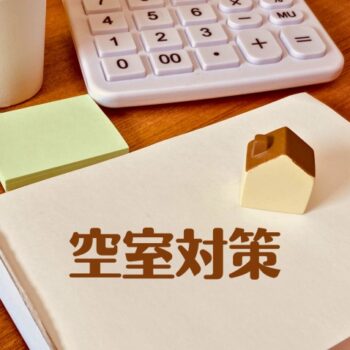土地を購入する際には、土地代金だけでなく、多くの諸費用がかかることをご存じでしょうか?
仲介手数料や登記費用、不動産取得税など、さまざまな費用が発生し、総額で 土地価格の5%〜10% にもなることがあります。
これらの諸費用を事前に把握せずに土地を購入すると、「思っていたより費用がかかりすぎた……」と後悔することになりかねません。
そこで、本記事では 「土地購入にかかる諸費用をシミュレーション!内訳や費用目安について解説」 というタイトルで、必要な諸費用の種類や金額の目安、費用を抑えるコツについて詳しく解説します。
適切な資金計画を立て、無理なくスムーズに土地購入を進めるためのポイントを押さえていきましょう。
1. 土地購入に必要な諸費用(諸経費)の内訳
土地を購入する際、単に土地の価格を支払うだけでは済みません。不動産の取引にはさまざまな手続きが必要となり、その都度、手数料や税金などの「諸費用」が発生します。
これらの諸費用は、一般的に 土地の購入価格の5%〜10% を占めると言われています。例えば、1,000万円の土地を購入する場合、50万円〜100万円程度の追加費用が必要になる計算です。
ここでは、土地購入時にかかる主な諸費用について、それぞれ詳しく解説します。
① 仲介手数料
1. 仲介手数料とは?
仲介手数料は、不動産会社を通じて土地を購入する際に支払う報酬です。仲介業者は、土地の紹介、契約の仲介、手続きのサポートなどを行い、その対価として手数料を請求します。直接売主から土地を購入する場合には発生しませんが、多くのケースでは不動産会社を介した取引となるため、この費用を考慮する必要があります。
2. 仲介手数料の計算方法
仲介手数料は、宅地建物取引業法に基づき、以下の計算式で上限額が決められています。
- 売買価格の3%+6万円(+消費税)(売買価格が400万円を超える場合)
例えば、1,000万円の土地を購入する場合、
- 1,000万円 × 3% + 6万円 = 36万円(税抜)
- 消費税(10%)を加えると、39.6万円 が上限額となります。
3. 仲介手数料を節約する方法
仲介手数料は、不動産会社ごとに異なり、割引を行っている会社もあります。また、「仲介手数料無料」の物件を扱う業者を利用するのも一つの方法です。ただし、無料物件の場合、売主が負担する形になっていることが多く、価格に影響している可能性もあるため、慎重に判断しましょう。
② 手付金
1. 手付金とは?
手付金とは、売買契約時に支払うお金で、一般的には売買価格の5%〜10%が相場となります。これは 契約の証拠金 のようなもので、契約が成立したことを示す役割を持ちます。
2. 手付金の具体例
例えば、1,000万円の土地を購入する場合、手付金の目安は以下のようになります。
- 5%の場合 → 50万円
- 10%の場合 → 100万円
この金額は、最終的な購入代金の一部に充当されるため、無駄にはなりません。しかし、契約を解除する場合には、手付金の扱いに注意が必要です。
3. 手付金の返還・没収のルール
手付金には「解約手付」という性質があり、以下のようなルールがあります。
- 買主の都合で契約を解除する場合 → 手付金は返還されず、売主が受け取る
- 売主の都合で契約を解除する場合 → 手付金の 2倍の金額を買主に返還
つまり、一度支払った手付金を取り戻すことは難しいため、契約を締結する前に慎重に検討する必要があります。
③ 印紙税
1. 印紙税とは?
印紙税は、不動産の売買契約書に貼付する印紙代のことです。契約書は 税法上の正式な文書 として扱われるため、一定の税額が課せられます。
2. 印紙税の税額一覧
契約金額に応じて、以下のように印紙税の金額が決まります。
| 契約金額 | 印紙税額 |
| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 10,000円 |
| 5,000万円超〜1億円以下 | 30,000円 |
例えば、1,000万円の土地を購入する場合、印紙税は1万円 です。(軽減されています。)
3. 印紙税を節約する方法
電子契約を利用すれば、紙の契約書が不要になるため、印紙税がかかりません。近年では、不動産取引でも電子契約を導入するケースが増えており、費用を抑える手段として活用できます。
④ 不動産取得税
1. 不動産取得税とは?
不動産取得税は、土地を購入した際に 一度だけ 支払う税金です。固定資産税評価額に基づいて計算されます。
2. 不動産取得税の計算方法
不動産取得税の計算式は以下のとおりです。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 3%
例えば、固定資産税評価額が500万円の土地を購入した場合、
- 500万円 × 3% = 15万円
これが不動産取得税として課税されます。
3. 特例、軽減措置について
令和9年3月31日までの間に宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)を取得した場合は、「不動産の価格の2分の1に相当する額」が「不動産の価格」となります。
例えば、上記2の場合
500万円×1/2×3%=7.5万円
これが不動産取得税として課税されます。
住宅用の土地として利用する場合、軽減措置が適用されるケースがあります。
次のうち、いずれか高い方の額から減額されます。
- 45,000円
- 土地の1㎡価格×住宅床面積の2倍(200㎡限度)×3%
購入前に、適用される軽減措置を確認しましょう。
特例や軽減措置は、頻繁に改正されますので、最新の情報をご確認ください。
⑤ 登記費用
1. 登記費用とは?
土地を購入した際には、名義を変更するために 所有権移転登記 を行います。その際にかかる費用が「登記費用」です。
2. 登記費用の内訳
登記費用には、以下のような費用が含まれます。
- 登録免許税(固定資産税評価額 × 1.5%)
- 司法書士報酬(5万〜10万円程度)
例えば、評価額1,000万円の土地を購入した場合、
- 登録免許税 = 1,000万円 × 1.5% = 15万円
- 司法書士報酬 = 約7万円
合計約22万円の費用がかかります。
3. 登記費用を抑える方法
自分で登記を行うことで、司法書士報酬を節約することが可能です。ただし、登記には専門知識が必要なため、一般的には司法書士に依頼するのが無難です。
2. 条件によっては必要になる可能性がある諸費用
土地を購入する際に必ず発生する諸費用とは別に、購入する土地の状況や利用目的によっては、追加で費用がかかるケースがあります。例えば、住宅ローンを利用する場合の手数料、測量が必要な場合の費用、農地を宅地に転用する際の費用などが挙げられます。これらの費用は、土地の条件によっては発生しない場合もあるため、事前に確認することが重要です。
以下では、発生する可能性のある諸費用について、それぞれ詳しく解説します。
① 住宅ローン手数料や保証料など
1. 住宅ローン手数料とは?
住宅ローンを利用する場合、金融機関に支払う「ローン手数料」が発生します。これは、ローン契約の手続きや事務処理にかかる費用であり、銀行によって手数料の金額が異なります。
2. 住宅ローン手数料の種類
住宅ローンの手数料には、主に以下の2種類があります。
- 定額型:一律で数万円〜数十万円の手数料を支払う(例:3万円〜55,000円)
- 定率型:借入金額の○%(例:融資額の2.2%)
例えば、3,000万円の住宅ローンを組む場合、
- 定額型(55,000円) の場合 → 5.5万円の支払い
- 定率型(2.2%) の場合 → 66万円の支払い
どちらが得かは、借入額や金融機関の条件によって異なるため、事前に比較しましょう。
3. 住宅ローン保証料とは?
保証料は、金融機関が住宅ローンの貸し倒れリスクを回避するために、保証会社を利用する場合に発生する費用です。保証料は「一括払い」と「金利上乗せ」の2つの支払い方法があります。
- 一括払い:最初に数十万円をまとめて支払う
- 金利上乗せ:毎月の返済額に上乗せされる(例:+0.2%)
保証料は 借入金額の2%程度 が相場で、3,000万円の借入であれば 約60万円 かかる計算になります。保証料不要のローンもあるため、選択肢を比較することが重要です。
② 測量費用
1. 測量が必要なケースとは?
土地の境界が不明確な場合、売買の前に測量を行う必要があります。特に以下のような場合には測量が必要になります。
- 土地の境界が曖昧な場合
- 隣地とのトラブルを避けたい場合
- 金融機関が測量図を要求している場合
測量を行うことで、後々のトラブルを防ぎ、安心して土地を利用することができます。
2. 測量費用の相場
測量費用は土地の状況によって変わりますが、一般的な相場は以下のとおりです。
| 測量の種類 | 費用相場 |
| 簡易測量(図面のみ) | 10万〜20万円 |
| 境界確定測量(隣地立会いあり) | 30万〜50万円 |
| 地積測量図の作成 | 50万〜80万円 |
広い土地や形状が複雑な土地の場合は、さらに高額になることもあります。
3. 測量の流れ
測量は以下の手順で行われます。
- 土地の現況調査(過去の測量図や公図の確認)
- 境界の確認(隣地所有者と立会い)
- 測量の実施(測量機器を使って計測)
- 図面作成と登記(必要に応じて登記手続き)
測量には時間がかかるため、早めに手続きを進めることが重要です。
③ 農地転用にかかる費用
1. 農地転用とは?
購入予定の土地が「農地」の場合、そのままでは住宅を建てることができません。農地を宅地として利用するためには「農地転用」の手続きを行い、行政の許可を得る必要があります。
2. 農地転用にかかる費用
農地転用には、以下の費用が発生する可能性があります。
- 申請費用(5万円〜30万円)
- 転用許可手数料(数万円〜)
- 開発行為に伴う負担金(場合によっては100万円以上)
たとえば、市街化調整区域の農地を宅地に転用する場合、追加でインフラ整備費用(上下水道や電気の引き込みなど)が発生することもあります。
3. 農地転用の申請方法
農地転用の手続きには、以下の流れがあります。
- 農業委員会に事前相談
- 転用申請書の作成
- 必要書類の提出(公図・測量図など)
- 許可の取得(通常1〜3ヶ月)
農地転用は自治体によって規制が異なるため、事前に相談することが重要です。
土地購入時には、必ず発生する諸費用だけでなく、状況によって追加で発生する費用があります。特に、住宅ローンの手数料や保証料、測量費用、農地転用費用などは、事前に確認しないと予想以上にコストがかかることもあります。
事前に確認すべきポイント
✅ 住宅ローンを利用する場合、手数料や保証料のシミュレーションを行う
✅ 境界が不明確な土地を購入する場合は、測量が必要かどうかチェックする
✅ 購入予定の土地が農地の場合、農地転用の許可を得る必要がある
これらの諸費用をしっかりと理解し、計画的な資金準備を行いましょう。
有限会社ひかり不動産は、埼玉県美里町を中心に本庄市や児玉郡内の「不動産売買」「不動産買取」自然素材の「注文住宅」「リフォーム」などを手がける会社です。
お気軽にお問い合わせください。

3. いくら用意するべき?土地購入にかかる諸費用をシミュレーション
土地を購入する際には、土地の価格だけでなく、さまざまな諸費用が発生します。これらの諸費用を把握せずに資金計画を立てると、予想以上の出費に直面し、予算オーバーになってしまう可能性があります。そのため、事前にシミュレーションを行い、どの程度の資金を準備すべきかを明確にすることが重要です。
ここでは、土地購入にかかる諸費用をシミュレーションし、具体的な目安を提示します。適切な資金計画を立てるためのポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。
土地購入にかかる諸費用の目安
1. 一般的な諸費用の割合
土地購入時の諸費用は、一般的に 土地価格の5%〜10% が目安とされています。これは、土地の価格に応じて変動し、以下のような計算が成り立ちます。
- 2,000万円の土地を購入する場合 → 100万円〜200万円
- 3,000万円の土地を購入する場合 → 150万円〜300万円
- 5,000万円の土地を購入する場合 → 250万円〜500万円
諸費用の金額は、購入する土地の状況や契約内容によって異なるため、具体的な内訳を確認することが重要です。
2. 諸費用のシミュレーション
例えば、3,000万円の土地を購入する場合、以下のような費用が発生すると考えられます。
| 項目 | 費用目安 |
| 仲介手数料 | 約105.6万円(税抜96万円) |
| 登記費用 | 約20万円〜30万円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 不動産取得税 | 約45万円(軽減措置適用時) |
| 固定資産税・都市計画税 | 約10万円〜20万円(購入時の日割り分) |
| 住宅ローン手数料(定率型) | 約66万円(借入額3,000万円×2.2%) |
| 合計 | 約250万円〜300万円 |
このように、土地購入価格の 約8%〜10% の諸費用がかかることが分かります。余裕を持った資金計画を立てることが重要です。
諸費用を抑えるためのポイント
1. 仲介手数料の割引を活用
不動産会社によっては、「仲介手数料無料」や「半額」のサービスを提供している場合があります。特に 売主が不動産会社 の場合は、仲介手数料がかからないことが多いため、事前に確認しましょう。
2. 登記費用を節約
登記手続きを自分で行うことで、司法書士の報酬を節約できます。ただし、手続きには専門知識が必要なため、不慣れな場合は慎重に判断することが大切です。
不動産登記について知りたい方は、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事:不動産登記とは?基本から手続き、費用、必要書類まで詳しく解説
3. 不動産取得税の軽減措置を利用
不動産取得税には軽減措置があり、一定の条件を満たせば負担を軽減できます。例えば、「住宅用地」として認められると、課税額が減額される可能性があります。
4. 住宅ローンの手数料を比較
住宅ローンの手数料は、定額型と定率型で大きく異なります。借入金額が少ない場合は定額型、借入金額が多い場合は定率型が有利になることがあるため、自分に合ったプランを選びましょう。
住宅ローンを利用すると住宅ローン控除を受けることができます。住宅ローン控除についてこちらの記事で詳しく解説していますので、ご興味あれば一度お読みください。
関連記事:住宅ローン控除とは?適用条件や申請方法を詳しく解説!2024年の変更点もチェック
資金計画を立てる際の注意点
1. 予想外の出費に備える
土地購入時には、想定していなかった費用が発生することがあります。例えば、以下のようなケースです。
- 土地の地盤が弱く、追加で地盤改良が必要になった
- 測量が必要で、追加の費用がかかった
- 上下水道の整備が不十分で、新たに設備投資が必要になった
このような事態に備えて、最低でも予算の10%程度の予備資金を確保 しておくことをおすすめします。
2. 諸費用込みでローンを組めるか確認
住宅ローンによっては、土地の購入費用だけでなく、諸費用を含めて借り入れできる場合があります。ただし、金融機関によって条件が異なるため、事前に相談しておきましょう。
3. 住宅取得資金贈与の特例を活用
親や祖父母からの資金援助を受ける場合、「住宅取得資金贈与の特例」を利用すれば、一定額まで贈与税が非課税となります。2024年の制度では 最大1,000万円まで非課税 となるため、資金援助を受ける予定がある場合は、活用を検討しましょう。
土地購入にかかる諸費用は、土地価格の 5%〜10% が目安です。事前にシミュレーションを行い、具体的な費用を把握しておくことで、予算オーバーを防ぐことができます。
資金計画を成功させるためのポイント
✅ 仲介手数料や登記費用を抑える方法を検討する
✅ 不動産取得税の軽減措置を活用する
✅ 住宅ローンの手数料を比較し、最適なプランを選ぶ
✅ 予備資金を確保し、予想外の出費に備える
これらのポイントを押さえ、スムーズな土地購入を実現しましょう。
4. 土地購入にかかる諸費用を踏まえて安心できる資金計画を立てよう
土地を購入する際には、土地の価格だけでなく、さまざまな諸費用が発生します。予算を土地代だけに設定してしまうと、手元資金が不足し、計画通りに購入が進まない可能性があります。そのため、購入前にしっかりと資金計画を立てることが非常に重要です。
資金計画を適切に立てることで、 予算オーバーを防ぎ、安心して土地購入を進めることができます。 ここでは、土地購入時に考慮すべきポイントや、資金計画の立て方について詳しく解説します。
土地購入をスムーズに進めて行くためのコツをご紹介しておりますので、合わせてお読みください。
関連記事:土地探しのコツ理想の土地を見極める10のチェックポイント
適切な予算の決め方
1. 資金計画の基本
土地購入時の資金計画を立てる際は、以下の3つの要素を考慮することが重要です。
- 土地代金
- 諸費用(手数料・税金・ローン費用など)
- 住宅建築費用(建物や外構工事など)
特に 土地代金と諸費用の合計が、自己資金と借入可能額の範囲内に収まるか をしっかりと確認することが大切です。
2. 土地代金の適正範囲を決める
多くの人が住宅ローンを利用して土地を購入しますが、 無理のない借入額 を設定することが重要です。
一般的に、住宅ローンの借入可能額は「年収の5〜7倍」が目安と言われています。
例えば、年収500万円の人が住宅ローンを利用する場合:
- 年収の5倍(2,500万円)なら、無理のない範囲
- 年収の7倍(3,500万円)になると、やや負担が大きい
また、自己資金の割合を考慮することも大切です。
土地代金+諸費用の合計のうち、2割以上は自己資金で準備できるのが理想 です。
諸費用を考慮した資金計画の立て方
1. 土地購入に必要な諸費用のシミュレーション
資金計画を立てる際は、諸費用を含めた総額を見積もることが不可欠です。例えば、3,000万円の土地を購入する場合の諸費用をシミュレーションすると、以下のようになります。
| 項目 | 費用の目安 |
| 仲介手数料 | 105.6万円 |
| 登記費用 | 20〜30万円 |
| 不動産取得税 | 45万円 |
| 印紙税 | 1万円 |
| 固定資産税・都市計画税(購入時の日割り) | 10〜20万円 |
| 住宅ローン手数料 | 60万円 |
| 合計 | 約250万円〜300万円 |
このように、土地の価格とは別に 5%〜10%の諸費用 を準備する必要があります。
諸費用のシミュレーションについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。
関連記事:土地購入にかかる諸費用をシミュレーション!内訳や費用目安について解説
2. 資金の準備方法
資金計画を立てる際には、自己資金とローンのバランスを考慮することが大切です。
- 自己資金を増やす → 頭金を増やし、借入額を抑える
- 住宅ローンを工夫する → 低金利のローンを選び、総支払額を抑える
- 補助金・減税制度を活用する → 住宅取得資金贈与の特例や不動産取得税の軽減措置を利用する
事前に利用できる制度を確認し、最大限活用することで、負担を減らすことができます。
無理のないローン計画を考える
1. 住宅ローンの借入額の決め方
住宅ローンを組む際は、「毎月の返済額が無理のない範囲か」を考慮することが大切です。
一般的に、 住宅ローンの返済負担率(年収に対する年間返済額の割合)は25%以内 に抑えるのが理想です。
例えば、年収500万円の人がローンを組む場合:
- 返済負担率20%(年間100万円) → 月々の返済額 約8.3万円
- 返済負担率25%(年間125万円) → 月々の返済額 約10.4万円
無理のない範囲でローンを組むことで、生活に余裕を持たせることができます。
2. ローンの種類と金利の比較
住宅ローンには、以下の3つのタイプがあります。
- 固定金利型(全期間同じ金利)
メリット:金利変動のリスクがなく、安心
デメリット:変動金利より金利が高め - 変動金利型(半年ごとに金利が見直される)
メリット:固定金利より低金利で借りられる
デメリット:将来的に金利が上がる可能性がある - 固定期間選択型(一定期間固定し、その後変動か再固定を選択)
メリット:一定期間は金利が安定する
デメリット:固定期間終了後に金利が上がるリスクがある
どのタイプが適しているかは、 将来のライフプランや金利動向を踏まえて判断 することが大切です。
余裕を持った資金計画を立てるためのポイント
1. 予備資金を確保する
土地購入後、思わぬ追加費用が発生することがあります。例えば、
- 土地の造成費用
- 建築費用の増加
- 固定資産税の支払い
これらに備えて、 最低でも50万円〜100万円の予備資金 を確保しておくと安心です。
2. ランニングコストを考慮する
土地購入後も、固定資産税や都市計画税、住宅ローンの返済が続きます。これらの ランニングコストを考慮し、毎月の収支をシミュレーション することが重要です。
土地購入時には、土地代金だけでなく諸費用がかかるため、 事前に資金計画を立てることが重要 です。
資金計画のポイント
✅ 土地代+諸費用を含めた総額をシミュレーションする
✅ 無理のないローン返済額を設定し、余裕を持つ
✅ 補助金・減税制度を活用し、コストを抑える
✅ 予備資金を確保し、突発的な出費に備える
これらのポイントを押さえ、計画的な資金準備を行うことで、安心して土地を購入することができます。
まとめ「土地探しのコツを押さえて理想の土地を見つけよう」
土地購入を進める際、希望に合う土地を見つけるのは簡単ではありません。しかし、 コツを押さえながら柔軟に条件を調整することで、予算内で満足できる土地を手に入れることが可能 です。
本記事では、土地が予算オーバーしたときの対応策として、以下の方法を紹介しました。
✅ 駅を一駅変える、または駅やバス停から離れた場所にする → 価格を大幅に抑えられる可能性がある
✅ 土地の面積を小さくする → コンパクトな設計を工夫すれば快適な住空間を確保できる
✅ 南向き以外の土地を選ぶ → 採光の工夫次第で快適な住環境が実現可能
✅ 旗竿地や変形地を検討する → 価格が安くなることが多く、プライバシー性も高い
✅ 建物の予算を調整し、土地の予算を増やす → 建築コストを抑える工夫で、理想のエリアでの土地購入が可能
土地選びは 条件の取捨選択とバランスが重要 です。「絶対に譲れない条件」と「柔軟に対応できる条件」を整理し、予算内で最大限希望に近い土地を選びましょう。
また、土地購入後の生活を考え、固定資産税や将来の維持費用も考慮しながら資金計画を立てることが重要 です。無理のない範囲で土地を選び、理想の住まいを実現しましょう。
有限会社ひかり不動産は、埼玉県美里町を中心に本庄市や児玉郡内の不動産の取り扱いと住宅建築を手掛ける創業50余年の地域密着企業です。土地や空家の買取りもお任せください。
住宅建築では、自然素材をふんだんに使用した注文住宅やリフォームを手掛けています。

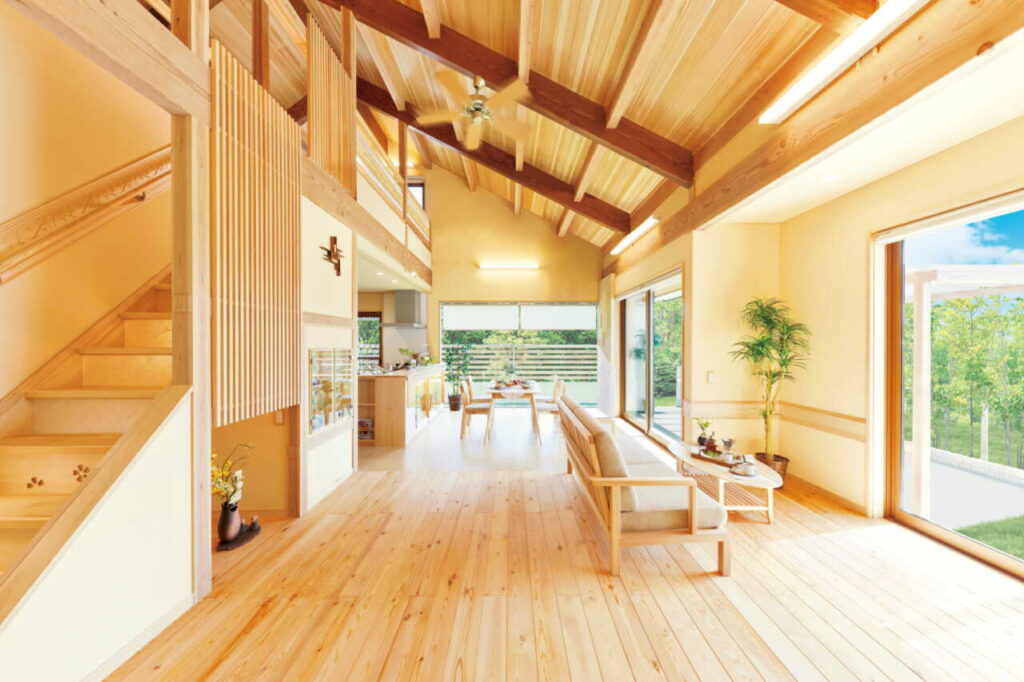
投稿者プロフィール

-
有限会社ひかり不動産 代表取締役
宅地建物取引士 二級建築士
埼玉県美里町に生まれ育ち
1987年~1990年:住宅建築・不動産会社勤務
1990年~:有限会社ひかり不動産
2000年~現在:有限会社ひかり不動産 代表取締役
不動産・住宅建築業界一筋で業界歴35年超のベテラン
長年の経験と今まで培ってきた事 そして、こだわりのある
「自然素材の家づくり」について皆様にお伝えします
最新の投稿
 不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう
不動産2025年4月15日空き家売却のベストな方法を知って将来のトラブルを未然に防ごう 家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド
家づくり2025年4月11日無垢材の種類の違いが丸わかり!木材選びに迷わないための完全ガイド 不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説
不動産2025年4月8日空き家売却における税金の基礎から特例までをわかりやすく解説 家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド
家づくり2025年4月4日家づくりの流れを完全攻略!家づくり初心者でも安心して進められるステップガイド